いよいよ私の PTA 活動も最後の年となりました。子どもが 1 年生の時に初めてPTA の「学年部役員」となり PTA を経験しました。2 年生の時に「会長」となり、6 年生の子どもが卒業する今年は最後の 1 年となります。
振り返ってみると、感染症の拡大やそれに伴う学校のギガスクール化など、大きな変革期に携わり、PTA の活動・認識そのものも大きく変化した 6 年だったと思います。
この 6 年の過渡期の中で、ある「結論」に至りました。その「結論」の前に、今年度の PTA 活動の現状をお伝えします。
今回の役員募集も、完全に強制はせずに立候補者のみで実施しました。今年度の立候補者数は 44 人。全校児童が 418 人ですので、10.5%の方が立候補してくれたことになります。ちなみに昨年度の立候補者数は 52 人 で約 12%でしたので、大きな変化はありませんでした。
私が PTA 会長を引き継いだ当時は、“強制”役員制度で、役員数は 83 人必要になっていました 全児童数から考えると約 20%…。PTA の役員は「子ども 1 人につき 1 回」という暗黙のルールがありましたので、20%ということは、5 年に 1 回の役員就任、小学校 6 年間に 1 人 1 回以上の強制されることが想定されていました。仮に強制とするのならば、適正は全校生徒 418 人÷6 学年とすると 16.6%(69人程度)が適正となりますよね。この適正数を考えずに、長きにわたり「不適正」を続けることで、強制で 2 回目になる人がいたり、どうしてもできない人にもやらせてしまったり…。そんなことが PTA 不要論に発展してしまったのではないかと思われます。以前の制度により、毎年毎年、不平不満を生むようなことを続けて、毎年毎年、PTA 不要!と叫びたくなる人を作り続けてしまったんですね・・・

ですが、光明もありました。以前のコラムでも書きましたが、感染症の拡大をきっかけに、各 PTA でも変革を遂げて、昨今の近隣 PTA の会長との会話では、役員数減・IT 化・組織改革・事業の縮小など、大きな変化が当たり前になってきたようです。
そして、完全な「立候補」制度に変えて 2 年になりましたが、改めて、日本は素晴らしいなと感じます(ちょっと大げさですが)。
なぜなら、今年度も 10%の方が「やってもいいよ」「活動したい」「手伝いたい」と自主的に手を挙げてくれるのですから。もちろん、役員募集についても工夫し、伝える頻度や内容も相当改善しました。一度だけの案内ではなく、学校のメール配信システム(安心メール)を使わせてもらって、役員募集締め切り 1 か月前から毎週、リマインドの案内をしました。途中経過もオープンにして、現在この部門(チーム)に「何人集まっています」「あと何人です」とか情報を公開しました。
立候補の後押しですね(笑)
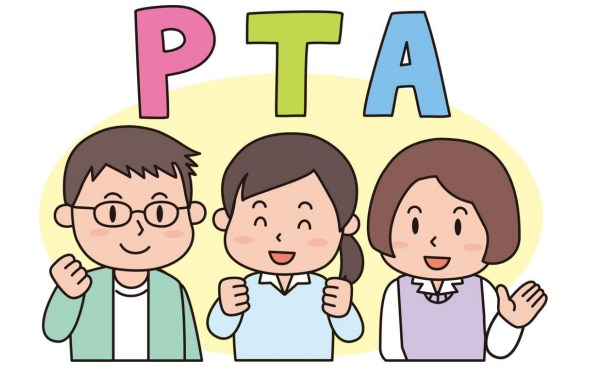
「PTA 活動への参加」は次のように大きく分けることができると思います。
・そもそも意識が高く、立候補してくれる人。
・「できるのかな…」と悩みながら立候補してくれる人。
・そして何よりも、PTA の活動が良くわからない人。
・仕事の都合などで、どうしても活動できない人。
それならば、
1.活動できない人には、活動はしてもらわなくても良い制度
2.積極的な方には、1 年と言わずに何度も活動できる制度。
3.PTA の活動がわからない人が大多数であることを前提として、「伝える」ことに注力し、理解促進を行い、悩んでいる人の背中を押せる制度。
こうしたことが、とても大事なんだとわかりました。
まだ 2 年間でデータとしては不十分かもしれませんが、約 10%の人は立候補してでも集まってくれて、活動できることがわかり始めました。ということは、全児童数の 10%前後がある程度の目安として、その人数でできる活動に絞っていけば、不平不満がたまらずに、楽しく活動ができると思われます。
最後に「結論」としてはやはり全国組織の PTA の理念でもある「できる人が できるときに できることを」がとても大事ですね。そして最後に持続可能性について役員の皆さんと考えたとき、気づいたことがありました。
少子高齢化で児童数は今後毎年減少していきます。いくら 10%の方が立候補してくれているといっても、極論を言えば、児童 100 人しかいない学校であれば、役員 10 人程度。児童 50 人なら役員 5 人です。近い将来は、間違いなく PTA が運営できない現実が訪れることになるでしょう。
私が退任した翌年に、PTA が解散する可能性すらあるかもしれません。でも、それは致し方ないことかな…と割り切れるようにもなりました。その時代時代において、約 10%の人が、楽しく活動し続けられるようであれば、PTA 活動を続ければいいと思います。

いつか、ちょっとこのままじゃ無理かもねっていう判断をせざるを得ない時には、「PTA 解散」を躊躇なく決断する時もあっても良いのではないでしょうか。
私たちはこう考えました。
「できる人が できるときに できることを」 ではなく
「やりたい人が、やりたいときに、やれることを」 にすることで、本当の有志団体に変わることができると思います。もっと持続可能性として前向きに考えると、PTA の考え方で「子どもの為」「学校の為」「地域の為」の活動なのかもしれませんが、もうすでに、保護者の方々は、仕事や家庭で限界の状態です。
あっという間の 6 年間を振り返ると、親としてだけでなく、自分自身の人生における、とても貴重な 6 年間を本当に楽しめたと思います。
PTA は親たちが、子どもの学校生活の間に「楽しんで子どもや学校とかかわりを持つ場」として人生をより充実させること!として活用すればよいのではないでしょうか。



* BSNラジオ 土曜日午前10時「立石勇生 SUNNY SIDE」の オープニングナンバーの後に「はぐくむコラム」をお伝えしています。
5月18日は、ファザーリングジャパンにいがた顧問の大堀正幸さんです。お楽しみに!






